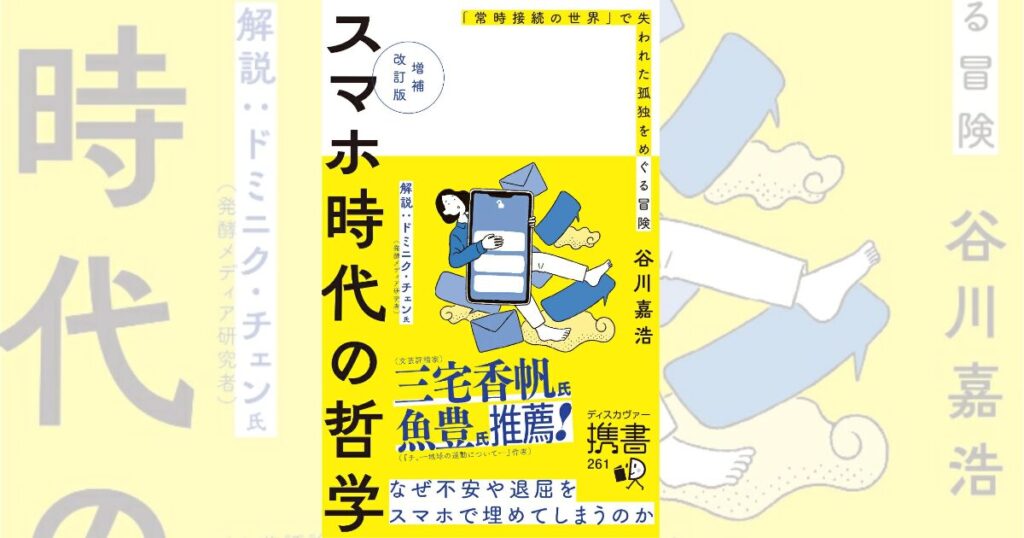
今回ご紹介する一冊は、
谷川嘉祐著 『スマホ時代の哲学「常時接続の世界」で失われた孤独をめぐる冒険』 です。
本書は、私の大学の生協の書店にふらっと立ち寄ったときに、表紙に惹かれるように手に取り、目次を見て、現代社会や現代社会における生き方に対する自分の考えを深めるのに適した書だと感じ、即購入いたしました一冊です。
本書の考えに準えながら、現代のスマホ時代における心の持ちようについて考えていきましょう!
- 形容しがたい生きづらさを抱えている人
- 罪悪感を感じながらもついつい長時間スマホを触ってしまう人
- 深く考える時間が減ったと感じる人
- 寂しさをふと感じることがある人
- 今の生活になんとなく違和感を感じている人

『「常時接続の世界」で失われた孤独』について
まず、本書のタイトルにもある、『「常時接続の世界」で失われた孤独』について追っていきます。
ひとつ留意しておきたいことは、一般的に孤独といえば、幾分かネガティヴなニュアンスを含んでいますが、ここではそのような含みはありません。
谷川氏は、ここでの孤独について、哲学者ハンナ・アーレントの考えを用いて、『心静かに自分自身と対話するように「思考」している状態』であると定義しています。
スマホならびにSNSの登場以後、常に全世界とつながっている、あるいはつながろうとできる時代になりました。
絶え間なく流れるXのポスト、Instagramのストーリーズやリール、YouTubeショートやTikTokなどのショート動画、夥しい量の広告、簡単に暇をつぶせるスマホゲーム…
市場は我々の快楽をいかに操作して、注意を向けさせるかに重点を置くようになりました。
言い換えると、我々の孤独をいかに削ぐかに対して尽力しているようにも感じます。
スマホならびにSNSは、孤独、すなわち自分自身との対話から遠ざけ、深く思考する機会を奪いつつあるのではないのでしょうか。
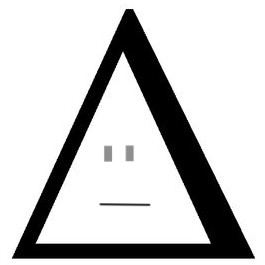
スマホって頭をフル回転したり、運動したりしているわけじゃないのになんか疲れちゃうよ~
このように感じる人もいるのではないでしょうか。
実際、自分もその一人で、何とも言えない曖昧な疲れがあることを認め、テレビを付けなくなったり、SNSのアイコンをホーム画面から消したりしました。
谷川氏は、現代の消費環境によって生活がマルチタスク化され、孤独が消失しているといいます。
このような無意識化でのマルチタスクは、知らず知らずのうちに脳と精神を疲弊させてしまうのかもしれません。
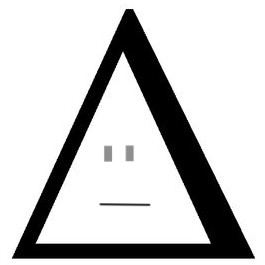
たまには、ゆっくり自分を見つめる時間も必要だね。
ちなみに、SNSは、資本主義の精神である合理的個人主義の精神を加速させることで、常に何かしておかなければならない、成長しなければならない、という強迫観念を生み出したようにも感じますが、この話はまた別の機会にしたいと思います。
ネガティヴ・ケイパビリティ
谷川氏は、孤独をもつために有用の力として、ジョン・キーツというイギリスの詩人が提示した「ネガティヴ・ケイパビリティ」という概念を導入します。
この「ネガティヴ・ケイパビリティ」は「結論づけず、もやもやした状態でとどめておく能力」として定義されています。
SNSなどによる短期的コンテンツの台頭などによって、深く考えるのではなく、手っ取り早く効果や快感を得ようとする世の中になりました。
人生のハウツーとしての自己啓発ブーム、前奏をそぎ落とした音楽の流行などにもみられるように、人生そのものにもタイパが求められるようになりつつあります。
このような忙しない生活の中で、幾分かでも、孤独、自己対話の時間をつくるために「ネガティヴ・ケイパビリティ」が重要だと考えます。
本書では、「ネガティヴ・ケイパビリティ」の実践例として「趣味」をあげています。
ここでの趣味とは、「社会生活とは切り離されたかのように、何かを作り、育てること」だと定義されています。
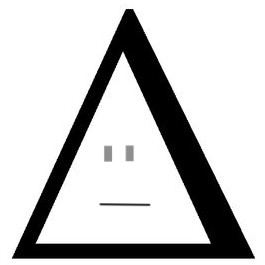
音楽、草花の栽培、執筆活動、絵画制作、筋トレ、裁縫とかもいいかもね。
私は、「ネガティヴ・ケイパビリティ」のもう一つの実践例として、勉学、学問をあげたいと思います。
様々な議論がある中で、勉学をする意味の一つとして、このことを考えております。
難解な問題に対峙したとき、深淵な思想を消化しきれないとき、数学書のなかなか埋まらない行間に悪戦苦闘するとき、私はこの「ネガティヴ・ケイパビリティ」を肌で感じているような気分になります。
数学や物理学の専門書を読むときには、見開き1ページに数時間かかることもあります。
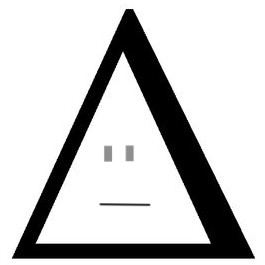
難しさ、モヤモヤと対峙したときに感じる、何とも言えない頭のぬくもりに、「ネガティヴ・ケイパビリティ」を感じるね~
このように、謎を安易に回収せずに繰り返し対峙する中で、孤独、自己対話が生じるのだと谷川氏は言います。
自己超越に向けて
今日の社会は、際限の無い競争や成長を我々に煽っています。
それによってメンタルヘルスのリスクを常態的に抱えた結果、寂しさに振り回されていると谷川氏は言います。
続けて、その寂しさから他者といようとするときに働くのは、他者へではなく自分への配慮であると谷川氏は言います。
なるほど、現代では、自己責任論や個人主義などから、関心が自分自身に向きやすい社会構造となっているのかもしれません。
SNSへの投稿で他者からの評価を過剰に得ようとすること、他人の脚色された輝かしい投稿を見て自分は全然だめだと悲観的になること、寂しさに棹差して常時連絡を取り続けること、これらは全て関心が自分に向きすぎているのではないのでしょうか。
自分への関心を乗り越えるところでも、先ほどの「ネガティヴ・ケイパビリティ」が発揮されるのではと思います。
難解な謎と対峙した時、自己の悩みのあまりの矮小さに気づくかもしれません。
また、自分は勝手に「研究の美徳」と呼んでいるのでありますが、上記の趣味や勉学を、SNSにアップするなどして自分を誇示するためにするのではなく、ただそのものを愛し、追求し、研究するところに本物の豊かさがあるのではないのでしょうか。
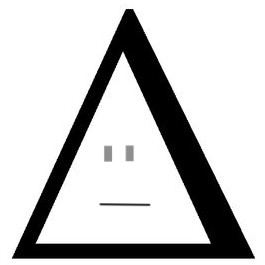
SNSにあげるためじゃなくて、そのこと自身、その瞬間を楽しみたいね。
20世紀を代表する知の巨人、バートランド・ラッセルは彼の著書『幸福論』で次のようにも語っています。
外的な事情がはっきりと不幸ではない場合には、人間は、自分の情熱と興味が内ではなく外へ向けられている限り、幸福をつかめるはずである。
以下の記事で『幸福論』についても取り扱っています。
また、ニーチェの「ツァラトゥストラ」における『超人』にも同じような自己超越の概念が含まれています。
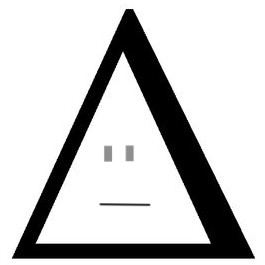
近代の書物にも似たような趣旨のことが語られているのは面白いね。
人間は、元来から、自己に関心が向きすぎてしまうきらいがあるのかもしれません。
その関心の向こう側には素晴らしい景色が広がっているのではないでしょうか。
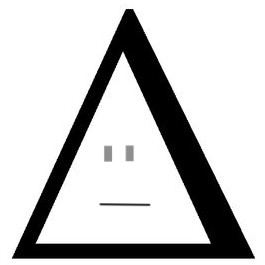
自分自身に対する関心を超えた先には、豊かな人生が待っているかも…!
おわりに
いかがでしたでしょうか。
少しでも興味深いと思ってくれた方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
中学入試にも出題されるほどの平易な語り口で親しみやすく、大変読みやすくはありますが、一筋縄にはいかず、もちろん深く考える必要がある一冊であるため、本書を読み進めること自体も「ネガティヴ・ケイパビリティ」の実践になりうるとも思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
 | 増補改訂版 スマホ時代の哲学 「常時接続の世界」で失われた孤独をめぐる冒険 [ 谷川嘉浩 ] 価格:1540円 |

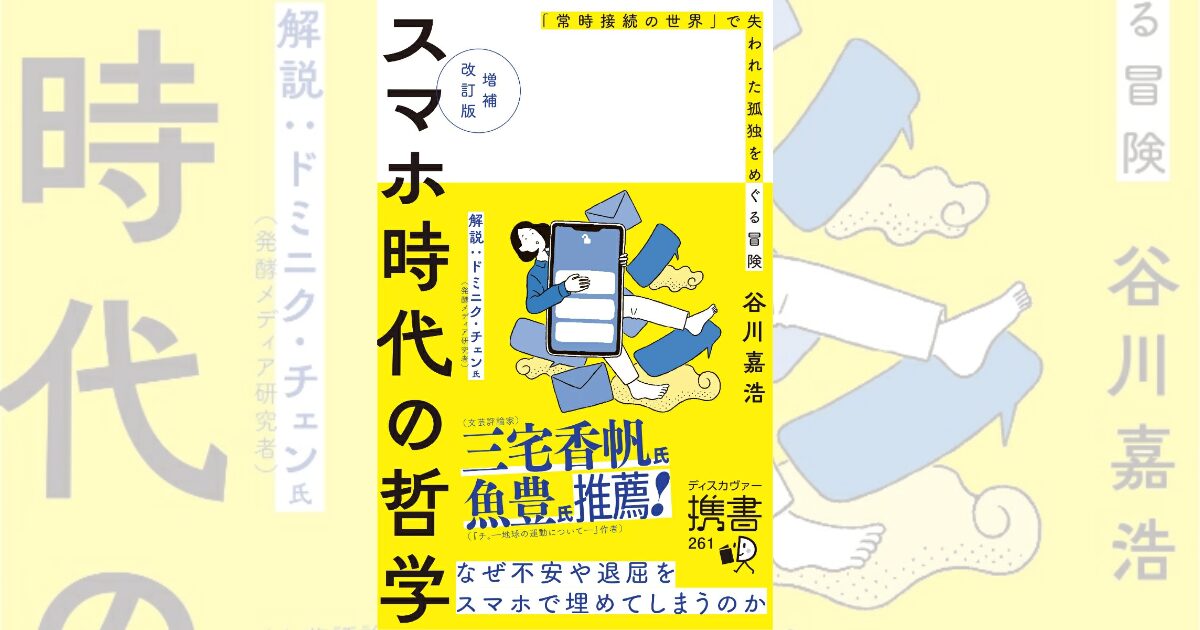


コメント