
今回ご紹介する一冊は、
バートランド・ラッセル著 『幸福論』 です。
本記事は前回の記事の続きとなっており、前回の記事をまだ見ていない方はそちらを先にご覧になってから本記事を見ていただきたいです。
以下に前回の記事のリンクを貼り付けておきます。
今回は、第二部の「幸福をもたらすもの」について見ていきます。
どうぞ最後までお付き合いいただきたいです。
幸福の秘訣
ラッセルは、第二部の始まりの章で幸福の秘訣についての概観を語っています。
まず、根本的な幸福は、他の何よりも、人やモノに対する友好的な関心に依存していると言います。
ここでの友好的な関心は、愛情の一つの形ではありますが、貪欲で、独占的なものではなく、人々を観察するのを好み、その個々の特徴に喜びに見出すような愛情のことです。
すなわち、自分と付き合う人々を支配しようとしたり、彼らから熱烈な称賛を得たいと考えるのではなく、彼らの興味や楽しみが存分に生かされる機会を与えたいと願うようなことです。
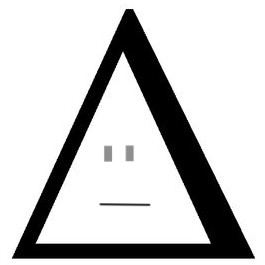
いわゆる、過保護、メンヘラ的な愛情ではないということだね。
そして、この章の最後で幸福の秘訣について以下のようにラッセルは結論づけています。
あなたの興味をできる限り幅広くせよ。そして、あなたの興味を惹く人やモノに対する反応を敵意あるものではなく、できるかぎり友好的なものにせよ。
この考えのもと、以下の幸福をもたらすものについて見ていきます。
幸福をもたらすもの
ラッセルは、幸福をもたらすものとして、熱意、愛情、家族、仕事、私心の無い興味、中庸を挙げています。
熱意
ラッセルは、幸福な人たちの最も一般的で他と区別される特徴として、熱意を挙げています。
人生に対する熱意がある人は、外界への自然な興味を持つことができ、また、そういった興味を持ち続けている限り、人生が楽しくなるとラッセルは言います。
関心を寄せるものが多ければ多いほど、自己没頭に陥ることが少なくなり、ますます幸福になるチャンスは増え、ますます運命に左右されることが少なくなります。
ところで、現代人は熱意を生み出す衝動が抑え込まれており、熱意を保つことが困難であるとしています。
未開人は、空腹になれば狩りをするというように直接的な本能に従っていますが、現代人は、仕事をして給料をもらうことは、将来の空腹を満たす手段であるという間接的な抽象概念、信念、熱意が動機となっています。
また、学校や会社による自由の束縛や、文明社会を成立させるのに必要なモラルなども衝動を制限しています。
ラッセルは、このような文明社会のハンディキャップのなかでも熱意を持ち続けるためには、エネルギーの大部分を費やしている内面の心理的葛藤から解放されることが必要だとしています。
熱意こそは、幸福と健康の秘訣である。
愛情
ラッセルは、愛されているという感情は、ほかの何よりも熱意を促進すると言います。
続けて、大多数の人は、愛されていないと感じると、世界に対する不安感を感じて臆病になり、ねたみや悪意を示すことでうっぷんを晴らすようになって、極端に自己中心的になると言います。
概して、愛情、称賛、好意の欠如は自己中心性をもたらすように思います。
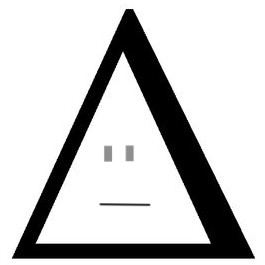
愛されたい、認めてもらいたい、「いいね」を稼ぎたい、といった感情は、こういった不安感からくる自己中心性のカモフラージュかもしれないね。
ラッセルは、この自己中心性から抜け出した人の特徴として、本物の愛情、すなわちお互いを幸福のための手段としてみるだけでなく、一つの幸福を共有する結合体だと感じる愛情を持っていると考えます。
愛されることと愛すること、それぞれが同量に存在するとき、それは最上の愛情となり、結果として全世界に対する興味深さをもたらすと考察しています。
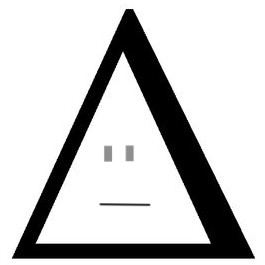
幼少期に十分な愛情を受け取らなかったラッセルなりの考察だと窺えるね。
熱意の欠如の主な原因の一つは、自分は愛されていないという感情である。
家族
ラッセルは、両親の子供に対する愛情と、子どもの両親に対する愛情は、幸福の最大の源の一つとなりうるはずであるのに、現代では逆にほとんど不幸の源となっていると言います。
これには、さまざまな理由がありますが、そのうちの一つとして女性たちに人の親になることを以前よりもはるかに重い負担に感じさせているということを挙げています。
また、現代世界において親であることの喜びを満喫することは、子どもに対して尊敬の態度を感じられる両親にのみ可能であるとも言います。
社会が母親に対して理不尽な犠牲を要求する場合は、子どもに対して、自分ができなかったことの埋め合わせを期待することになりがちですが、このような専制的、または自己犠牲的な母親は子に対して非常に利己的であります。
こういった子どもは自分のものであるという所有欲や権力欲は、子どもに対して尊敬の態度を感じられる両親には立ち現れないでしょう。
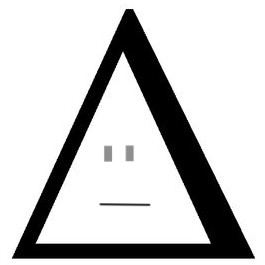
最近の、いわゆる「教育ママ」も子どもに対してこのような利己性を抱いているのかもしれないね。
仕事
ラッセルは、仕事について、退屈の予防策として望ましいものであるが、仕事が面白い場合は、単なる退屈しのぎよりもはるかに高度な満足が与えられると言います。
ここでは、仕事を面白くする要素として、技術の行使と建設の二つを挙げています。
まず、技術の行使についてでありますが、変化に富むか、もしくは無限に向上させうる技術の熟練を必要とする仕事は全て楽しいものにできると言います。
続けて、建設は、幸福の源として、この技術の行使よりも一段と重要なものであるとしています。
この建設性をもつ仕事は、仕事が完成したときに一つのモニュメントとしての何かが残る、すなわち最後の状態は一つの目的を具体化している状態である仕事です。
ただ、ここで幸福を手に入れるためには、人生に首尾一貫した目的があり、その人生の目的と仕事の目的が一致する必要があると説いています。
そして、この首尾一貫した目的は主に仕事によって具体化されるのです。
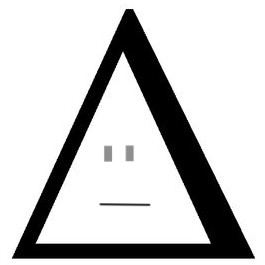
人生と仕事の目的が一致していなければ、ふと何のために仕事をしているかわからなくなるときがありそうだね。
私心の無い興味
まず、私心の無い興味とは、一人の人間の生活の根底をなす主要な興味ではなく、その人の余暇を満たし、より真剣な関心事のもたらす緊張を解きほぐしてくれるような二次的な興味のことを指します。
ラッセルは、私心の無い興味は、気晴らしになるだけでなく、釣り合いの感覚を保つのに役立つと考えます。
自分の職業、仲間内、仕事の種類などに熱中するあまり、それらは人間の活動全体の微々たる部分に過ぎないということを忘れがちになります。
そうなると、自分の重要性をあまりに誇大化してしまい、不当な悲劇を描いてしまう。
そうではなく、もっと幅広い興味を持ち、人生のバランスを保つべきであると説いています。
また、私心の無い興味は、悲しみを紛らわす効用もあると言います。
生活がごく少数の興味で満たされてしまっていたら、その興味が悲しみに満たされてしまったとき、思考の切り替えはなかなか難しいです。
悲しみに耐えるために、幸福なとき、余裕があるときに、ある程度広い興味を養うことで、思考のチャンネルが増え、そこが辛くなった時の精神の安息地になるとラッセルは考えます。
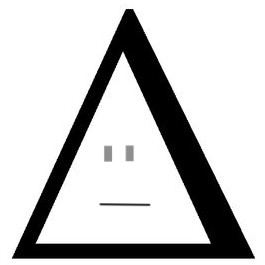
ラッセルが自殺の淵に立ったとき、彼を救ったのは数学に対する純粋な興味だったね。
人生の意義と目的をそっくり偶然の手にゆだねるといった、そんな狭い激しさを私たちの人生に与えるべきではない。
中庸
中庸というのは、面白くない教えであるが、実に多くの事柄において真実の教えであるとラッセルは言います。
特に、努力とあきらめのバランスにおいて、この中庸が必要になります。
幸福は達成されるもの、獲得するものであるというラッセルの考えから、努力は幸福に必要なものであるとわかるが、あきらめにも、幸福の獲得において果たすべき役割があるとしています。
避けられる不幸は座視しない一方、避けられない不幸に時間と感情を浪費してはなりません。
あきらめには、絶望に根差すものと不屈の希望に根差すものの二種類あり、前者は悪く、後者は良いと言います。
失敗や挫折をしたとしても、長期的にみるとその挑戦は他のだれか、そして人類に貢献したのかもしれない、といった希望に根差したあきらめは完全なる敗北ではありません。
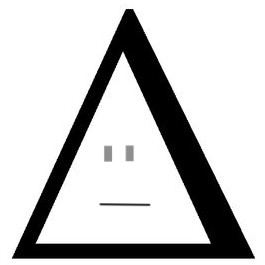
不屈の希望に根差すあきらめには、没我的な希望があるということだね。
自己欺瞞で支えながら生きる努力を捨て、苦痛を伴うが、真実を見つめながら生きる態度が永続的な幸福の条件であると説きます。
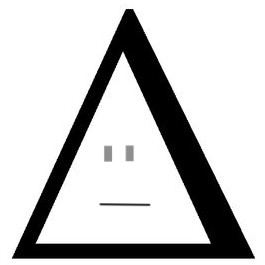
「人事を尽くして天命を待つ」の精神が大事だということだね。
没我的に生きること
以上のように、ラッセル幸福論の第一部、第二部を見てきましたが、幸福の条件として一貫したものを感じられたのではないのでしょうか。
私は、その条件として、没我的精神、あるいは自己超越的観点に見ました。
すなわち、自分に対する熱烈な興味を超えて、外界に対する興味に根差すことがラッセルの考える幸福に必要不可欠な条件ではないかと思います。
私の二十年という短い人生経験ではありますが、その経験の中でも、メンタルに不調をきたしている人のほとんどが自分に関心が向きすぎているような気がしてなりません。
我々の生きるこの今日では、メンタル面の不調を抱いている人が増えているということをよく耳にすることがあるかと思われます。
SNS登場以後、全世界の人と無意識的に比較してしまう構造になってしまいました。
比較というのは専ら自己を中心に置いた思考法であるため、この社会では幾分か構造的にメンタル面に対するデメリットがあります。
また、受験勉強もメンタルを壊しやすい(実際に、私の周りの人々にも受験期にメンタルが不安定だったという人は一定数いました…)ように思われますが、それは、受験が相対的かつ自己責任的なシステムであり、必要以上の比較を誘引するものであること、また自分のブランド化対決になっていることに起因しているのではないでしょうか。
模試であいつに負けた、自分はこの学校の中では下の方の成績だ、こんなに勉強しているのにちっとも成績が伸びないじゃないか…といったように自己が誇大化してしまう。
学問に対する純粋な興味を抱きその自然な欲望に従って勉学に励むべきであるのに、どうも学問がつまらないもので、将来のキャリアのために仕方なく苦心して励まなければならないという観念が社会的に浸透しているように思えます。
そうであるから、勉学が、これだけ高い点を取った、こんな難問を解いた、難関大学に合格した、などという「自分のブランド化対決」のツールでしかなくなる傾向にあるのではないでしょうか。
少し話がそれてしまいましたが、受験勉強を例に出したようなことが、他の分野でも少なからず起こっており、それがメンタルを壊す種になっていると思います。
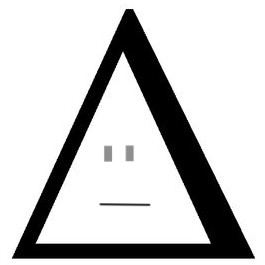
自分を悲劇のヒロイン風に仕立てている人も、「なんで自分だけ…」「どうしてこんなに頑張っているのに…」などと自分に関心を向けすぎているように思うよ。
このように比較を誘引する現代の社会では、ラッセルの説く幸福への障害が多数存在しますが、外界への純粋な興味を抱いて、評価や競争などが介入しないチャンネルを自分の中に持っておくことが幸福へのカギの一つではないでしょうか。
谷川嘉祐氏の『スマホ時代の哲学「常時接続の世界」で失われた孤独をめぐる冒険』でも似たような議論をしていますのでよければこちらも拝見していただきたいです。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
自分の悩みの正体に光が当たり始めた、そう感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回と前回の記事では、本書の要旨をかいつまんでご紹介したため、より深く本書を味わいたい方はぜひ原典を手に取っていただきたいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
| ラッセル幸福論/ラッセル/安藤貞雄【1000円以上送料無料】価格:1001円 (2025/9/3 09:22時点) 感想(0件) |

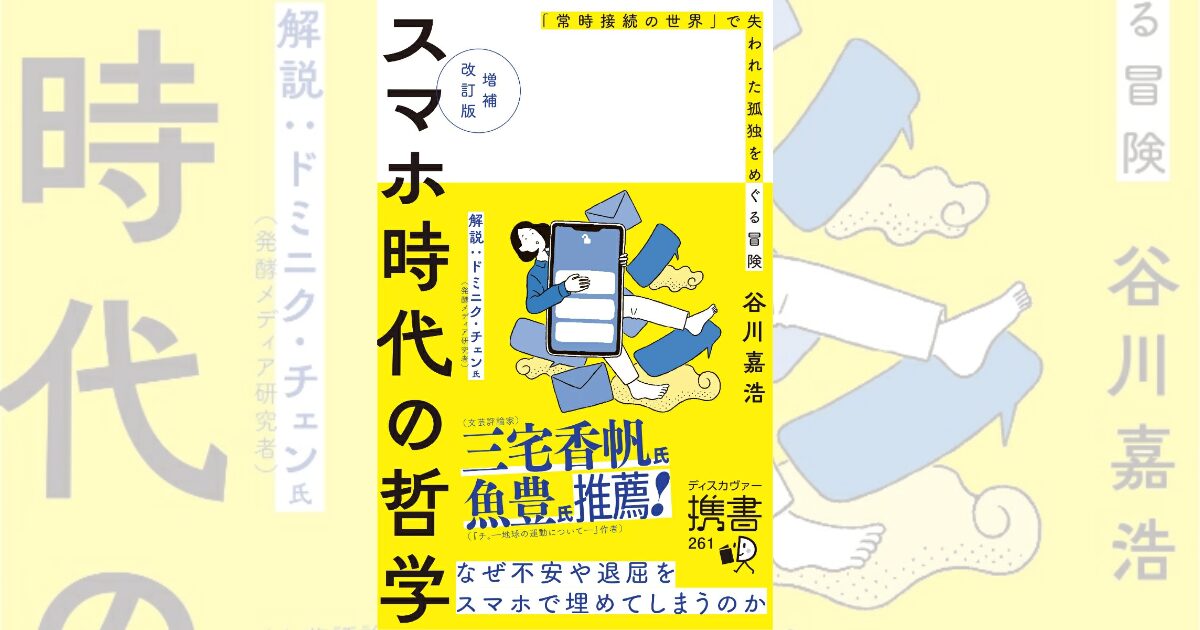


コメント